【1987年】
「ある意味では、この10年でやったことは全て試遊に過ぎなかった」(エド・エドワーズ)
10年前のあの夏の日と同じように、7月2日からメリーランド州ボルチモアで行われた「オリジンズ'87」の会場で、『MegaTraveller Box Set』は公開されました(※この会場では、ウィリアム・キースによるSeeker社製の『トラベラー』10周年記念ポスターも出展されています)。箱の中にはやはり同じように『Players' Manual』『Referee's Manual』『Imperial Encyclopedia』の3冊のルールブックと、10年の時を経て微妙に変化した「スピンワード・マーチ宙域図」が収められていました。
![]()
![]()
![]()
Digest Group Publications(DGP)のフューゲートとトーマスが『MegaTraveller』の制作で採った手法は、過去の全『トラベラー』ルール・データの「総集編」でした。ゲームルールの核には自分たちが練り上げた共通判定書式(UTP)を採用し、過去に発表された上級キャラクター作成ルール、スクエア制戦闘ルール(『Snapshot』や『アザンティ・ハイ・ライトニング』)、改定貿易ルール、ライブラリ・データなどを全て盛り込み、『トラベラー』10年間の集大成として仕上げました。確かに『Mega』を冠するに値する分量であり、それでいてルールは緻密で、これはファンや市場が求めていた物と製作期間の最大公約数を取れば妥当と言える判断でしたが、裏を返せばルールや表の肥大化を招き、詰めの甘さが散見される仕上がりとなってしまいました。
そして最大の問題点が「誤植の多さ」でした。これはDGPとGDWが当時使用していたワードプロセッサ・ソフトウェアの間にデータの互換性がなく、DGP側が仕上げた原稿をGDW側が印刷のために「手作業で」入力し直していたことに起因しています。これにより、GDWは8頁もの正誤表小冊子の発行(ただし1990年9月になって)や、『Challenge』誌でのサポートに追われることになりました。誤植が取れ切るのは1992年発売の第3刷までかかっています。
「この10年間でレフリーもプレイヤーも、宇宙のどこに何があり、どのような危険があるか知ってしまったはずだ。スリルのあるゲームを楽しむためには、何か劇的な変化が必要だったんだ。それが『メガトラベラー』なのさ」
(マーク・ミラー)
さらに、前述したストレフォン皇帝一家暗殺事件によって宇宙設定にも大幅な変動が加えられました。突然の暗殺で1100年の歴史を誇る〈帝国〉は分裂し、諸勢力が相争う時代となったのです。兄の不可解な死体の上に皇位を継承したルカン、暗殺を決行しながら〈帝国〉を掌握できなかったイレリシュ大公デュリナー、両者の皇位継承を認めない貴族が担ぎ出した先々帝の血を引くマーガレット、自領防衛のためにルカンの命令を拒み独立を選んだワリニア公クレイグと〈新ヴィラニ帝国〉、中央から切り離されて自活を迫られたデネブ大公(を領内安定のために詐称した)ノリス、大裂溝の淵で決起した「本物の」ストレフォン、〈帝国〉を見限ったアンタレス連盟、に加えて、空前の大混乱に乗じて侵攻を続けるヴァルグル海賊やアスランやソロマニ連合……と、〈帝国〉全土が戦場と化しました。『Challenge』誌のトラベラー・ニュースサービスは毎号「反乱(Rebellion)」の推移を報じ、同時にショートシナリオや新設定の公開などにより、第五次辺境戦争以上の戦乱の宇宙がレフリーとプレイヤーに提供されました。
最終的に『MegaTraveller』は総出荷数26642セット(※加えて、後に単品売り版が各9000部前後出荷されています)を数えるヒット作にはなりましたが、かつてと比べれば、業界自体の勢いの陰りを示すようでもありました。
マイケル・ミケシュ(Michael R. Mikesh)と、1984年~1985年にかけて全11号が発行されたファンジン『Working Passage』の編集者であったエド・エドワーズ(Ed Edwards)によって「History of the Imperium Working Group(HIWG)」が結成されました。HIWGはDGPと連携し、〈帝国〉に限らず既知宇宙全ての歴史や設定を起こしていくための団体で、最盛期には全世界で200名を越えた会員の中にはクレイ・ブッシュ(Clay Bush)、ドン・マッキニー(Don McKinny)、ジオ・ジリナス(Geo Gelinas)といった重要人物が含まれています。後に下部組織としてHIWG-UK(イギリス)、HIWG Australia、HIWG-NZ(ニュージーランド)も作られました。
またパソコン通信のGEnieやTML、会報『Tiffany Star』『AAB Proceedings』『Starburst』『Starport』『Kfan Uzangou』などで会員同士の交流や情報交換、設定公開が積極的に行われました。
このように『メガトラベラー』は、アマチュア(実質セミプロ)団体HIWGが起こした設定をサードパーティDGPが拾い上げ、システムやシナリオに組み込んだ物を原作者マーク・ミラーの下で製造元GDWが販売する(逆にミラーからHIWGに要望を出すこともありました)、というRPG業界でも稀有な体制で制作が続けられました。この三者協調は初めは非常に上手くいっていましたが、しかし作品世界を動かす権限を終始GDWが握っていたことが、彼らの関係を徐々に歪にしていったのです。
ファンジンでは『Jumpspace』(全6号)、『Security Leak』(全5号)、およびジオ・ジリナスによる『Traveller Times』が創刊されています。特に『Traveller Times』は、途中『Terra Traveller Times』と名を変えて1991年まで存続しました。紙としては全43号が刊行され、以後電子化がなされましたが現在では全て消失しています。
なお余談ですが、この頃ジョー・フューゲートは公式設定にある単語や文法を用いて、まるでヴァルグルのように喋ることができるようになりました。ただし喉に非常に負担がかかり、日頃の練習が欠かせないようです。
【1988年】
![]() GDWから『Rebellion Sourcebook(反乱軍ソースブック)』と『Referee's Companion』が発売されました。前者は反乱の経緯や各反乱勢力の解説、後者はボックスセットに収まり切らなかった各種設定情報(エイリアン・モジュール総集編など)やルールが詳述されています。
GDWから『Rebellion Sourcebook(反乱軍ソースブック)』と『Referee's Companion』が発売されました。前者は反乱の経緯や各反乱勢力の解説、後者はボックスセットに収まり切らなかった各種設定情報(エイリアン・モジュール総集編など)やルールが詳述されています。
DGPからは車両データ集『101 Vehicles』、入手困難だった「グランドツアー」第1話~第4話をまとめた単行本『The Early Adventures』、レフリー・スクリーンに加えて(ザルシャガル宙域を舞台にした唯一の)シナリオ小冊子が付属した『Referee's Gaming Kit』、宇宙船運用ルール・設定集『Starship Operator's Manual Vol.1』が発売されました。
『Challenge』誌が季刊から隔月刊に移行しました。また、第34号から誌面内の『Traveller』表記が『MegaTraveller』に切り替わり、第35号からはGDW製に限らないSF-RPG総合誌として再編されました。これはかなり異例なことではありますが、意図としては他社ゲームのファンをGDW作品に引き込むことが推察されます。自社製RPGを優先的に扱う方針に変化こそなかったものの、相対的に『メガトラベラー』の地位が低下したともいえます。
日本では『タクテクス』第58号から「グランドツアー」の翻訳連載が開始されています。年末には『トラベラー・アドベンチャー』も発売されました。
【1989年】
GDWから『COACC』が発売されました。惑星の大気圏と低軌道を守る「空軍」に焦点を当てた初の資料集で、解説と様々なデータが収録されています。
製品番号から推測すると、この『COACC』の次には『Flashback: Historical Adventuring in the Imperium's Past』というシナリオ集が計画されていました。PCは冷凍睡眠による時間旅行者となって、恒星間戦争、暗黒時代の始まり、帝国建国、内乱の始まりと終わり、超能力弾圧、ソロマニ・リム戦争といった歴史的事件に立ち会い、最終的に帝国暦1300年の未来から「過去」を俯瞰する、という構成だったようです。この企画は1992年に再浮上したようですが、結局この時も立ち消えとなりました。
DGPからは『World Builder's Handbook』が出されました。これは『トラベラー』時代の資料集『Grand Survey』『Grand Census』(1986年~1987年)を合本して調整を施したもので、半分は偵察局による惑星探査活動の解説や追加装備、残りの半分はかつての『偵察局』や『メガトラベラー』搭載の上級星系作成システムよりも詳細な、星系の文化や宗教観にまで踏み込んだ作成のできる改定ルールが収められています。
『Challenge』第39号に「Special Supplement: The Hinterworlds」が掲載されました。ヒンターワールズは中立星系や小国家群が多くを占める宙域で、〈帝国〉の反乱から離れたい人々(と新規入門者)に向けて掲載されたようです。宙域の歴史や小国家の解説、かつての『Supplement 3: The Spinward Marches』と同等の宙域内全UWPや星域情報が収められています。
そしてこの号から後、チャールズ・ギャノン(Charles E. Gannon)によるヒンターワールズ宙域を舞台にしたショートシナリオが少しの間掲載されるようになります。
Paragon Softwareが『トラベラー』初のコンピュータゲーム『MegaTraveller 1: The Zhodani Conspiracy』を開発しました(販売はMicroproseから)。『メガトラベラー』のルール自体を(簡略化しながらも)そのまま取り込んだことに称賛の声が挙がったものの、一方で戦闘システムの作りがまずく、『Computer Gaming World』誌では「歴代4位の酷いゲーム」と(1996年発売の第148号にて)評されてしまいました。
ちなみにこれは、『メガトラベラー』を冠しながらも反乱以前の時代を描いた唯一の作品です。
パソコン通信GEnieに、ジョー・フューゲートが『Atlas of the Imperium』を基にした膨大な量のUWPデータを公開しました(DGPからフロッピーディスクで販売する予定でしたが、実現しませんでした)。1994年にGEnieのFTPサーバーであるSunbaneに転載されて広まったことから今では「Sunbane」と呼ばれるこの標準世界書式(UWP)集は、欠けた部分を補う手法の違いで幾つかの派生版を産みましたが、現在にまで至る既知宇宙設定の根幹を成す最重要資料となりました。ただしデルファイ宙域のUWPに「10043」が多発したり、マッシリア宙域にTL16世界が乱立したりしたのは、当時から問題視されていました。
日本では『タクテクス』誌の「グランドツアー」連載が第6話をもって事実上打ち切られ(ただし第6話として掲載されたものは本当は第7話です)、佐脇洋平による『メガトラベラー』紹介連載に切り替えられました。また、ホビージャパン版『トラベラー』としては最後のサプリメント『トラベラー・ロボットマニュアル』が発売されています。日本でもいよいよ『メガトラベラー』時代の到来となるのですが、諸事情により発売までは随分と待たされることになります(その間は細々とTNSの翻訳記事が掲載されました)。
一方で、Diseños Orbitales社からスペイン語版『トラベラー』が発売されました(※1987年の段階でミラーが言及しているのでかなり遅れたようです)。内容は1977年版の翻訳らしいのですが、表紙も含めて再編集が行われ、チャート小冊子やスペイン語版のスピンワード・マーチ宙域図、珍しいものとしてはペーパーフィギュアが付属していました。
その後は『Suplemento 1: 1001 Personajes』『Aventura 1: Kinunir』『Libro 4: Mercenario』が発売されたものの、そこで展開は途絶えました。
【1990年】
![]() GDWから艦船データ集『Fighting Ships of the Shattered Imperium』、キャンペーン・シナリオ『Knightfall(ナイトフォール)』が発売されました。後者は反乱激戦区のマッシリア宙域で行方不明となった貴族の謎を追う話なのですが、日本語訳された際に随所に訳者から指摘が入るという穴だらけの展開と、まさに労多くして功少なしな締め方は、各地で数々の悲喜劇を生んだようです。実はこの作品は「太古種族の秘密」に代わる新シリーズの序章に過ぎなかったのですが、続きや結末が明らかになることは結局ありませんでした。
GDWから艦船データ集『Fighting Ships of the Shattered Imperium』、キャンペーン・シナリオ『Knightfall(ナイトフォール)』が発売されました。後者は反乱激戦区のマッシリア宙域で行方不明となった貴族の謎を追う話なのですが、日本語訳された際に随所に訳者から指摘が入るという穴だらけの展開と、まさに労多くして功少なしな締め方は、各地で数々の悲喜劇を生んだようです。実はこの作品は「太古種族の秘密」に代わる新シリーズの序章に過ぎなかったのですが、続きや結末が明らかになることは結局ありませんでした。
ちなみに『Knightfall』以降のGDW製品は、全て発行部数が5000部に減らされています。『トラベラー』時代は1万部を切ることがなかったことを考えると、寂しい数字ではあります。
DGPからはまず、ヴランド宙域を舞台にしたキャンペーン・シナリオ集『The Flaming Eye』が登場しています。前述の『Knightfall』もそうですが、DGPが提唱した「ナゲット・システム」によるシナリオ進行が特徴です。
そして『メガトラベラー』版エイリアン・モジュールである「MegaTraveller Alien」シリーズの刊行が『Vilani & Vargr: The Coreward Races』から始まりました。その質は極めて高く、特にヴィラニ人に関する設定資料は現時点ではこの本だけという貴重なものです。そして翌年には第2弾の『Solomani & Aslan: The Rimward Races』も発売されています。
![]() 雑誌『Travellers' Digest』の方では、第21号をもって「グランドツアー」が(作品内で)12年間に及んだ長旅を終えて遂に完結し、翌年発売分からは『MegaTraveller Journal』に改題して主にデネブ領域の設定掘り下げに特化しました。
雑誌『Travellers' Digest』の方では、第21号をもって「グランドツアー」が(作品内で)12年間に及んだ長旅を終えて遂に完結し、翌年発売分からは『MegaTraveller Journal』に改題して主にデネブ領域の設定掘り下げに特化しました。
(※なお日本では『タクテクス』第74号において、「グランドツアーの面々も、ダイジェスト誌11号以後は崩壊した帝国での冒険を続けています」との情報が流されましたが、最終話は帝国暦1112年なので当然崩壊はしていません。問題の第11号から対応システムが『メガトラベラー』に移行したことによる勘違いと思われます)
この年からAdjutantという(自費出版同然の)ところから『Striker』用の車両・航空機データ集が、翌年まで全10冊が刊行されました。
また、RAFM社からは28mmサイズの宇宙船メタルフィギュアの製造・販売が始まっています。最終的に30種類ほど制作されたようです。
『Challenge』第43号から編集長が交代し、長年編集長を務めたローレン・ワイズマンは副編集長に退きました。
また、『Far & Away』誌が創刊されています。キース兄弟が記事や表紙に参加し、雑誌広告も打つなど華々しくデビューしましたが、発行はわずか第2号で潰えたようです。ファンジン『Coreward』も創刊されました(これも全2号でしたが)。
![]()
![]()
![]()
年末、日本語版『メガトラベラー スターターセット』がホビージャパンから発売され、それを受けて『RPGマガジン』第9号にて特集記事が組まれました。(日本語版全てで)翻訳は佐脇洋平が、表紙絵は漫画家・山田章博が手掛けています。しかし原文由来の多くの誤植に加えて日本語版固有の誤植も抱えてしまい、その訂正は有志がパソコン通信上で行った上で、1993年発売『RPGマガジン』第39号~第41号掲載の「メガトラベラー正誤表」まで待つことになります(そしてその後、正誤表を小冊子として添付した単品売り版が販売されました)。
また、富士見書房から小説『トラベラー(1) 戦乱のアウトリーチ宙域』が発売されましたが、これは前述の「Not in Our Stars」を佐脇洋平が和訳したものです。翌年には『逃亡の惑星(Become the Hunted)』も刊行されましたが、展開はそこで途絶えました。
(※解説文を寄せた安田均が「(著者は)いまは“メガトラベラー”小説に取り組んでいる」と記しているのは、「別の出版社(※New Infinities Productionsのこと)」から出された「同じシリーズ」の数を「二冊」としていることから、1988年に既に発売されている『Tales of Concordat, Book 3: Revolt and Rebirth』を指してしまっていると思われます)
余談ですが、Steve Jackson Gamesのスティーブ・ジャクソンは自社紙『Roleplayer』第19号において、1981年発売の第2版が絶版になって以降幻となっていた『Triplanetary』の復活を宣言します。「オリジンズ'89」の会場でマーク・ミラーと交渉して後に権利を得たこと、1991年に発売の見込みであること、単なる復刻ではなく自社のGURPS Spaceとの連携も企図した改定がなされることが明かされました。
……が、後に追信として、当時のSJGはかの「合衆国シークレットサービス強制捜査事件」の渦中にあったこと、また試作はなされたものの社外での試遊は行われなかったことが記され、結局『Triplanetary』が復活することはありませんでした。
【1991年】
この年はGDWにとって、様々な意味で転機となる年となりました。まず8月発売予定で制作が進んでいたシナリオ集『Rebels’ Tales』が4月に中止され、製品番号に2つ目の欠番が生じました。これは元々「Rebellion Sourcebook 2」として企画され、帝国暦1125年までの反乱の推移とその時代のショートシナリオ数本を収める予定でした。しかしマーク・ミラーは、そもそもこの本の必要性には懐疑的だったと伝えられています。
そしてそのマーク・ミラーが、この年GDWを退社しています。彼は当時副業で保険代理店を営んでおり、そちらに専念してGDWから給与を受け取ることをやめたのです。依然としてミラーはGDWの大株主であったので会社に対する影響力は保持していたものの、彼の退社に前後して『メガトラベラー』に、そして目をかけていたDGPに重大な影響がありました。
実のところ、GDWは売上不振から1990年の段階で事業閉鎖を考えていました。ウォーゲームは全盛期の2割に落ち込み、『Twilight: 2000』はまだまだ現役なものの、不振だった『2300AD』や『Space: 1889』は前年で新製品の投入をやめてしまいました。
SF-RPG界隈も大きく変わっていました。特に1988年発売の『Cyberpunk』(R. Talsorian Games)が火付け役となった「サイバーパンク」の隆盛はスペースオペラを過去のものとし、一方でそのスペースオペラもWest End Gamesの『Star Wars』(1987年)に大きく侵食されていました。
しかし、1990年8月に起きたイラクによるクウェート侵攻がGDWの転機となります。1991年1月初頭にフランク・チャドウィックが書き下ろした『The Desert Shield Fact Book』が、同月17日のアメリカ軍による「砂漠の嵐作戦」開始によって大ベストセラーとなったのです。ニューヨーク・タイムズ紙による売上ランキング1位を獲得し、ある意味GDW最大のヒット作と言えるかもしれません。この本で得た多額の資金で息を吹き返したGDWは、社員や設備を増強して反転攻勢を狙います。
![]() ミラーに代わって『メガトラベラー』の担当となった新規雇用者デイビッド・ニールセン(David Nilsen)が9月末に初出社した際に見たものは、数枚の「崩壊した帝国」図を含むイラストと、表紙原稿のコピー、そして倉庫にあった5000部分の完成した表紙カバーでした。そして彼に与えられた仕事は、来る出版のために原稿を編集することでした。
ミラーに代わって『メガトラベラー』の担当となった新規雇用者デイビッド・ニールセン(David Nilsen)が9月末に初出社した際に見たものは、数枚の「崩壊した帝国」図を含むイラストと、表紙原稿のコピー、そして倉庫にあった5000部分の完成した表紙カバーでした。そして彼に与えられた仕事は、来る出版のために原稿を編集することでした。
実はGDWはミラーの退社前にチャールズ・ギャノンを中心にして、従来と異なりDGP関係者を一切使わずに(※一部のHIWG会員は関わっています)この『Hard Times(ハードタイムズ)』を、そしてそれに続く2作品を書き上げさせていたのです。
ミラーやDGPはそれぞれ、(少なくともミラーは1988年の段階で)帝国暦1125年時点での反乱終結の構想を持っていました。ミラーは、ストレフォンとマーガレットの滅亡、ソロマニ占領地の中で孤立したヴェガ自治区と〈帝国〉中央を繋ぐ1本の「スター・レーン」というアイデアを持ち、一方DGPは、ダイベイの陥落、デュリナー=マーガレット同盟とソロマニ連合との停戦合意、アンタレスの超新星爆発による滅亡、といういずれも「小国分裂による現状維持」を思い描いていました。
しかしギャノンがミラーに提示したものはそれらよりも遥かに過酷で現実的な、〈帝国〉が軍事的ではなく経済的に自壊するというものでした。ミラーはそれを認めて自身の「1125年停戦」構想を取り消し、『Rebels’ Tales』の発売中止に至ったと思われます。
「マークはどんな構想に対しても寛大で、私の創造性を抑え込んだりもみ消したりするような職権は決して用いなかった」
(チャールズ・ギャノン)
この『Hard Times』によって、設定は反乱の最中の帝国暦1122年から一気に1128年に進み、もはや反乱勢力の誰も〈帝国〉の再興は望めない、荒廃した「苦難の時代」が描かれました。国家に代わって個人(つまりプレイヤーが)が英雄となりやすくなることを企図した激変でしたが、これによりDGPは深刻な打撃を受けます。これまでのミラーを間に入れたGDWとの協調体制を反故にされただけでなく、発売を準備していた資料集・シナリオが路線変更によって出版する機会を逸してしまったのです。
1990年の段階で、DGPは以下の作品の出版計画を持っていました。
『Campaign Sourcebook 1: The Black Duke』:
1989年末発売予定。イレリシュ宙域を舞台にした『トラベラー・アドベンチャー』型の商人キャンペーン・シナリオで、前述のデュリナー=マーガレット同盟締結の話にも触れられるはずでした。1990年に入って『Rebels’ Tales』との入れ替えでキャンセルされたようです(※この時に同時に、『Knightfall』や『Solomani & Aslan』とも絡めたDGP側の反乱終結構想も立ち消えとなったと思われます)。
『Manhunt』:
キャンペーンシナリオ「Onnesium Quest」三部作の第1部で、Gen Con '90(1990年8月)で発売予定でした。銀河で最も希少な物質「オンネシウム118」が多く眠るとされる伝説の小惑星帯ははたしてどこに? そして、鉱脈を見つけたと言い残した宇宙鉱夫はどこに消えたのか? 第2部『Antares Down』も1990年秋発売予定だったようです。
『Robots & Cyborgs』:
1990年夏発売予定。ロボット作成ルールの改定と人体の機械化ルールの追加、『101ロボット』相当のロボット型録を収録する予定でした。ロボット作成ルールに関しては2011年に草稿が発掘され、有志によって『MegaTraveller Robots: Shudusham Concords Revisted』として編纂されました。
『Grand Explorations』:
1990年夏発売予定。深宇宙探査や植民地化の解説、未知世界用に調整された星系作成システム、探査シナリオに向いたフラニ宙域の設定と新知的種族、4つの探検シナリオが収録される予定でした。
『Starship Operator's Manual Vol.2』:
1990年秋~冬発売予定。ジャンプドライブや宇宙船整備についての解説、宇宙船の入手について、宇宙船の駆動方式について、100トン偵察艦の派生型等々が盛り込まれる予定でした。
他にも「Alien」シリーズの第3~5巻である『Zhodani & Droyne: The Psionic Races』『K'kree & Hiver: The Exotic Races』『Humans & Nonhumans: The Minor Races』、反乱の主役たちのインタビュー記事を中心に構成した総集編『The Best of the Travellers' Digest』が1991年以降の発売予定で計画が組まれていましたが、これら全てが「時期外れ」となってしまいました。これら未発売作品の原稿料などによって、DGPの財務は大きく苦しめられました。結果的にDGPから出たサプリメント本はこの年発売の『Solomani & Aslan』が最後となり、その後は『MegaTraveller Journal』の発行に専念しつつ、裏でとある企画を動かしていました……。
この年、SeekerがSeeker Gaming Systemsに社名変更しています。SGSは1985年の創業以来『Research Facility』『Empress Marava』『Gazelle Class Close Escort』といった、『メガトラベラー』(や『2300AD』)向けに様々な建物や艦船のデッキプラン(兼ミニチュアゲーム用ゲームボード)を提供してきました。また、表紙にウィリアム・キースを起用するなどキース兄弟とも近く、彼らが版権を持つ「スコティアン・ハントレス号」シリーズなどの復刻も手掛けています。
しかし翌1992年に活動を停止してしまいました。
『メガトラベラー』の広報紙『Imperial Lines』がGDWから発刊されました(実質HIWG制作ですが)。8頁の中に設定や追加装備、ショートシナリオが収録されています。また、スピンワード・マーチ宙域に隣接する「フォーイーヴン宙域」の設定作りを個々のレフリーやプレイヤーに正式に委ねた、後の「Free Sector宣言」に繋がる重要資料も掲載されています。
なお、第2号も年内に公開されたものの、1992年6月発行予定だった第3号は延期され、第3/4号合併号として仕切り直して同年11月発行に向けて制作が続けられましたが、結局幻となりました(第5号の計画もあったようです)。
![]() 日本では9月に『反乱軍ソースブック』が発売されています。また、『RPGマガジン』ではキャンペーン・シナリオ「ガシェメグの嵐」が連載されました(全9話)。シナリオの舞台となる「ガシェメグ宙域」はマーク・ミラーの許可を得て日本独自設定での展開がなされ、簡素ながら一部の星域図・UWPの公開もされています。
日本では9月に『反乱軍ソースブック』が発売されています。また、『RPGマガジン』ではキャンペーン・シナリオ「ガシェメグの嵐」が連載されました(全9話)。シナリオの舞台となる「ガシェメグ宙域」はマーク・ミラーの許可を得て日本独自設定での展開がなされ、簡素ながら一部の星域図・UWPの公開もされています。
(※ちなみにこの「ガシェメグの嵐」では“「本物の」ストレフォンはクローン”説が採用されていますが、一方HIWGではエド・エドワーズが“「本物の」ストレフォンはクローンだが、暗殺されたストレフォンも実はクローン(オリジナルは10年前に死亡)で、ルカンに捕殺されなかったクローンがあと1人行方不明となっている(しかも超能力者)”という設定を起こしています。そしてGDWは……)
ドイツ語版『トラベラー』最後の作品『Splitter des Imperiums』が発売されました。これは『トラベラー』と『メガトラベラー』の橋渡しをする独自編集本で(といってもJTAS誌の翻訳記事も多いですが)、ルールの変更点の解説、デッキプラン、異星生物などが収録されています。
ドイツでは(と言うより日本以外では)『メガトラベラー』は翻訳されなかったため、ドイツでの『トラベラー』の展開はこれで一旦途絶えることになります。
マーク・ミラーによると、1991年末以降の発売予定で『トラベラー』初の公式小説が企画されていたようです。ヒューゴー賞受賞の大物編集者が携わり、大手出版社から様々なテーマ(太古種族、第五次辺境戦争、反乱等々)の小説が出るようでしたが、結局何一つ発売はされませんでした。
コンピュータゲーム第2弾である『MegaTraveller 2: Quest for the Ancients』が発売されました。前作の反省を活かしてシステムを刷新し、またマーク・ミラーが直接製作に関与しています(前作では資料提供のみ)。今回は上々の評価を得られ、直接の続編である『MegaTraveller 3: The Unknown Worlds』の制作も予告されましたが、1992年に製作元のParagonがMicroproseに買収されたのが響いてか、結局発売されることはありませんでした。
【1992年】
「我が社の製品名がこれから起こることを不気味に暗示していた。『苦難の時代(Hard Times)』『荒れ狂う波(Troubled Waters)』『危険な旅路(Dangerous Journeys)』『異議あり(Challenge)』と……」
(デイビッド・ニールセン)
『ハードタイムズ』時代としては初の(そしてGDWとしても初の二つ折り判の)シナリオ集『Assignment: Vigilante』が発売されます。荒廃したディアスポラ宙域を征く星間傭兵ヴィジランテの活躍を描いたこの作品ですが、著者のはずであるチャールズ・ギャノンは「自分の原稿の大部分が削除され、『劇的に』書き直された」と後に語っています。同じく発売された宙域設定集『Astrogator's Guide to the Diaspora Sector』についても「希望の兆しを示すはずだった」と振り返っています。
というのも、ギャノンはまず『ハードタイムズ』で反乱を事実上終結させ、その後の200年に及ぶ復興期を新作「Surveyor」で描く構想を持っていました(『ハードタイムズ』本文中にもその伏線が伺えます)。また、フランク・チャドウィックが1990年頃から開発を進めていたものの発売中止となったミニチュアゲーム「Star Viking」は、その中間の帝国暦1130年頃に位置付けられることになっていたようです。これにはGrenadier社との提携も見据えていた上に、ギャノンによる小説執筆の契約もされていました。
ギャノンの構想では、サーベイヤー(探査者)たちが傭兵スター・ヴァイキングと共に、かつての『リヴァイアサン』のように未知と化したも同然の危険な宇宙の荒野に飛び込み、海賊らと戦って人々を助け、やがて復興と成長を遂げた彼らの前に機械の体で永遠の命を得たルカン率いる「暗黒帝国」が立ち塞がり、イリジウム玉座の奪還を目指す戦いが始まる……というものだったようです。
「イリジウム玉座への帰還は新たな帝国を象徴していただろうし、“短い夜”の終わりを明示したことだろう。もっとも、それが良い企画だったかどうかは全く別の問題だが……」
(チャールズ・ギャノン)
しかし、ギャノンのGDWでの仕事はミラーの退社とともに終了しています。なぜなら1991年から開発が始まったとされる新作“Traveller: Take 3”は、彼が全く想定していなかった「新時代」を舞台としていたからです。
「事実、JTASやChallenge誌の一番人気はトラベラー・ニュースサービスだった。彼ら(GDW)のファンは彼らが築いた宇宙を熱愛していたのに、その歴史を根本的に終わらせて別のものとして再開させるのは、それに至った議論は理解するにしても決して理解できない商売上の決定だったと思う」
(チャールズ・ギャノン)
![]() 9月発売の『Challenge』第64号に、突如として「When Empires Fall」という8頁の記事が掲載されます。その内容は、何かを示唆した詩、「帝国暦1130年、〈帝国〉は滅んだ。」という衝撃の一文から始まる文章、そして人工知能や宇宙船の自動応答装置(transponder)に関する設定が記され、最後に『Twilight: 2000』第2版由来のゲームシステムを搭載した『Traveller: The New Era』が1993年2月に発売される(※実際は6月までずれ込みました)という予告が載りました。
9月発売の『Challenge』第64号に、突如として「When Empires Fall」という8頁の記事が掲載されます。その内容は、何かを示唆した詩、「帝国暦1130年、〈帝国〉は滅んだ。」という衝撃の一文から始まる文章、そして人工知能や宇宙船の自動応答装置(transponder)に関する設定が記され、最後に『Twilight: 2000』第2版由来のゲームシステムを搭載した『Traveller: The New Era』が1993年2月に発売される(※実際は6月までずれ込みました)という予告が載りました。
こうして反乱は、そして『メガトラベラー』は事実上の終焉を迎えたのです。この路線変更がミラーの退社後に行われたのは間違いありません。これがミラー主導なのかGDW主導なのかははっきりしていませんが、ギャノンの証言の中でミラーが以前から“Traveller 3rd Edition”を準備していたくだりがあるので、ミラー退社後にGDW側で“3rd Edition”が“Take 3”に差し替えられた可能性は高そうです。また、HIWG会員は1991年末の段階で路線変更のことを知らされています。
「ノリスに伝えてくれ。すまなかった、と――」
(皇帝ストレフォンの遺言)
GDWが制作した最後の『メガトラベラー』作品である『Arrival Vengeance: The Final Odyssey』は、ノリス大公の特命を受けて3年間に及ぶ航海に旅立ったライトニング級巡洋艦アライバル・ヴェンジェンスの軌跡を体験するシナリオ(の概要)集です。かつての「グランドツアー」とは奇しくも逆回りに、ある「重要人物」と共にデネブ領域を出てアスラン領を経由し、ワリニア公クレイグやデルファイ公マーガレットといった反乱の当事者と会見し、荒廃した帝国中央を突っ切り、最後は「本物の」ストレフォンに「託されて」大裂溝を踏破してデネブに帰還する……という、来るべき「新時代」に向けての地ならしと伏線張りの要素が強く感じられます。また、長らく秘密にされてきた「本物の」ストレフォンの正体が明かされるという意味でも重要な資料です(とはいえ、今さら明かされてもどうにもなりませんが……)。
![]()
![]() 日本では『ナイトフォール』が発売され、『RPGマガジン』にてリプレイ『サイオニック・バスターズ!』が連載開始されました(全6回)。反乱とは距離を置き、超能力者PCたちが同じく超能力を駆使する宗教団体への潜入任務を行うという派手さを求めた、ある意味「邪道」(本文より)な話でした。
日本では『ナイトフォール』が発売され、『RPGマガジン』にてリプレイ『サイオニック・バスターズ!』が連載開始されました(全6回)。反乱とは距離を置き、超能力者PCたちが同じく超能力を駆使する宗教団体への潜入任務を行うという派手さを求めた、ある意味「邪道」(本文より)な話でした。
そして、このリプレイ連載終了と共に『RPGマガジン』での記事掲載は散発的となり、翌年発売の第44号の記事と『ハードタイムズ』の発売をもって日本における『メガトラベラー』は終了します。構想では日本独自のレフリー・スクリーン、「ガシェメグの嵐」の単行本化、『Referee's Companion』や『The Flaming Eye』の翻訳が挙げられていましたが、全て幻となりました。
【1993年】
Sword of the Knight Publicationsから『Traveller Chronicle』誌が創刊されました(刊行数は年2~4)。掲載された重要資料としては、かつてFASAが展開していたファー・フロンティア宙域の設定紹介や、チャールズ・ギャノン自らが執筆した「Astrogator's Update to Diaspora Sector」、リーヴァーズ・ディープ宙域の幻の設定集「A Pilot's Guide to the Caledon Subsector」が挙げられます。
米国のヘビーメタルバンド「The Lord Weird Slough Feg(現Slough Feg)」は、文字通り『トラベラー』を主題としたアルバム『Traveller』をリリースしました。「The Spinward Marches」「High Passage/Low Passage」「Vargr Moon」といった曲が12曲収められています。各地の批評を見る限りでは、音楽ファンから非常に好評をもって受け入れられたようです。
![]() 前号から1年振りに発行された『MegaTraveller Journal』第4号には、ウィリアム・キース書き下ろしの大規模キャンペーン・シナリオ「Lords of Thunder」が丸々収録されました。これは元々SGSから発売する予定だったものを買い入れた、という経緯があります。旅の舞台はゲイトウェイ宙域に(Judges Guildのものに上書きして)設定され、これまで距離的事情から絡みの少なかった知的種族ククリーが大きく関わってきます。
前号から1年振りに発行された『MegaTraveller Journal』第4号には、ウィリアム・キース書き下ろしの大規模キャンペーン・シナリオ「Lords of Thunder」が丸々収録されました。これは元々SGSから発売する予定だったものを買い入れた、という経緯があります。旅の舞台はゲイトウェイ宙域に(Judges Guildのものに上書きして)設定され、これまで距離的事情から絡みの少なかった知的種族ククリーが大きく関わってきます。
ちなみにこの「Lords of Thunder」が、長らく『トラベラー』を支え続けたウィリアム・キースにとって最後の作品となりました。その後、ウィリアムは以前から平行して手掛けていた小説業に専念して数々の作品を残します。
「『Traveller: The New Era』の登場で、我々は『トラベラー』のサポートをやめることにしました。これには多くの理由がありますが、最も重要なのはゲームの針路を自分たちで決めたいという望みです」
(ジョー・フューゲート)
そしてこの第4号は、DGP最後の出版物でもありました。いえ、彼らはこれを最後にする気はなかったのです。彼らは『A.I.』という超未来(もしくは超過去)の「サイエンス・ファンタジーRPG」を計画し、着々と準備を進めていました。当初予定では1991年10月の発売で、それから遅れに遅れてはいたものの雑誌やイベント会場で広報活動を念入りに行い、華々しく発売させるはずでした。DGPの悲劇は、優れたゲームシステムや設定をいくら作り出しても、ゲームの「針路」自体を自分たちで決められずに翻弄されたことにありました。自社作品の『A.I.』なら、それができるはずだったのです。
しかし、信じがたいことに『A.I.』の原稿を収めたハードディスクが破損する事故により、出版は頓挫してしまいます。この話が本当かどうかはさて置いても、『A.I.』を出せずに借入れ金を返済する見込みがなくなったDGPは、いくつかの原稿料遅配トラブルを抱えつつ、ジョー・フューゲート1人だけの債権整理企業として消えていきました……。
……が、まだDGPをめぐる物語は終わりません。1994年にフューゲートのもとをロジャー・サンガー(Roger Sanger)なる者(※といってもHIWG会員だと思われます)が訪れ、DGPの資産(版権や商標を含む)の買収を持ち掛けます。9ヵ月間に及ぶ交渉の末、数千ドルでDGPはサンガーの物となりました。その後のフューゲートはゲーム業界から身を引き、趣味だった鉄道模型の世界で活躍しています。
そして1996年、サンガーとDGPが歴史の表舞台にもう一度だけ現れるのですが……その前に「新時代」について語らねばなりません。「新時代」がもたらしたものは、反乱以上の混乱と凋落だったのです。
「もうよせ、報道を止めても無駄だ。全てが終わったんだ」
(帝国暦1130年243日付TNS記事より)
(「トラベラー40年史(3) 新時代、そして暗黒時代へ…」に続く)
(文中敬称略)
「ある意味では、この10年でやったことは全て試遊に過ぎなかった」(エド・エドワーズ)
10年前のあの夏の日と同じように、7月2日からメリーランド州ボルチモアで行われた「オリジンズ'87」の会場で、『MegaTraveller Box Set』は公開されました(※この会場では、ウィリアム・キースによるSeeker社製の『トラベラー』10周年記念ポスターも出展されています)。箱の中にはやはり同じように『Players' Manual』『Referee's Manual』『Imperial Encyclopedia』の3冊のルールブックと、10年の時を経て微妙に変化した「スピンワード・マーチ宙域図」が収められていました。
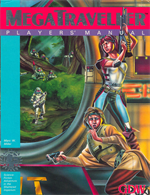
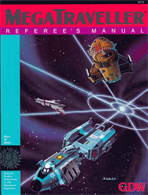

Digest Group Publications(DGP)のフューゲートとトーマスが『MegaTraveller』の制作で採った手法は、過去の全『トラベラー』ルール・データの「総集編」でした。ゲームルールの核には自分たちが練り上げた共通判定書式(UTP)を採用し、過去に発表された上級キャラクター作成ルール、スクエア制戦闘ルール(『Snapshot』や『アザンティ・ハイ・ライトニング』)、改定貿易ルール、ライブラリ・データなどを全て盛り込み、『トラベラー』10年間の集大成として仕上げました。確かに『Mega』を冠するに値する分量であり、それでいてルールは緻密で、これはファンや市場が求めていた物と製作期間の最大公約数を取れば妥当と言える判断でしたが、裏を返せばルールや表の肥大化を招き、詰めの甘さが散見される仕上がりとなってしまいました。
そして最大の問題点が「誤植の多さ」でした。これはDGPとGDWが当時使用していたワードプロセッサ・ソフトウェアの間にデータの互換性がなく、DGP側が仕上げた原稿をGDW側が印刷のために「手作業で」入力し直していたことに起因しています。これにより、GDWは8頁もの正誤表小冊子の発行(ただし1990年9月になって)や、『Challenge』誌でのサポートに追われることになりました。誤植が取れ切るのは1992年発売の第3刷までかかっています。
「この10年間でレフリーもプレイヤーも、宇宙のどこに何があり、どのような危険があるか知ってしまったはずだ。スリルのあるゲームを楽しむためには、何か劇的な変化が必要だったんだ。それが『メガトラベラー』なのさ」
(マーク・ミラー)
さらに、前述したストレフォン皇帝一家暗殺事件によって宇宙設定にも大幅な変動が加えられました。突然の暗殺で1100年の歴史を誇る〈帝国〉は分裂し、諸勢力が相争う時代となったのです。兄の不可解な死体の上に皇位を継承したルカン、暗殺を決行しながら〈帝国〉を掌握できなかったイレリシュ大公デュリナー、両者の皇位継承を認めない貴族が担ぎ出した先々帝の血を引くマーガレット、自領防衛のためにルカンの命令を拒み独立を選んだワリニア公クレイグと〈新ヴィラニ帝国〉、中央から切り離されて自活を迫られたデネブ大公(を領内安定のために詐称した)ノリス、大裂溝の淵で決起した「本物の」ストレフォン、〈帝国〉を見限ったアンタレス連盟、に加えて、空前の大混乱に乗じて侵攻を続けるヴァルグル海賊やアスランやソロマニ連合……と、〈帝国〉全土が戦場と化しました。『Challenge』誌のトラベラー・ニュースサービスは毎号「反乱(Rebellion)」の推移を報じ、同時にショートシナリオや新設定の公開などにより、第五次辺境戦争以上の戦乱の宇宙がレフリーとプレイヤーに提供されました。
最終的に『MegaTraveller』は総出荷数26642セット(※加えて、後に単品売り版が各9000部前後出荷されています)を数えるヒット作にはなりましたが、かつてと比べれば、業界自体の勢いの陰りを示すようでもありました。
マイケル・ミケシュ(Michael R. Mikesh)と、1984年~1985年にかけて全11号が発行されたファンジン『Working Passage』の編集者であったエド・エドワーズ(Ed Edwards)によって「History of the Imperium Working Group(HIWG)」が結成されました。HIWGはDGPと連携し、〈帝国〉に限らず既知宇宙全ての歴史や設定を起こしていくための団体で、最盛期には全世界で200名を越えた会員の中にはクレイ・ブッシュ(Clay Bush)、ドン・マッキニー(Don McKinny)、ジオ・ジリナス(Geo Gelinas)といった重要人物が含まれています。後に下部組織としてHIWG-UK(イギリス)、HIWG Australia、HIWG-NZ(ニュージーランド)も作られました。
またパソコン通信のGEnieやTML、会報『Tiffany Star』『AAB Proceedings』『Starburst』『Starport』『Kfan Uzangou』などで会員同士の交流や情報交換、設定公開が積極的に行われました。
このように『メガトラベラー』は、アマチュア(実質セミプロ)団体HIWGが起こした設定をサードパーティDGPが拾い上げ、システムやシナリオに組み込んだ物を原作者マーク・ミラーの下で製造元GDWが販売する(逆にミラーからHIWGに要望を出すこともありました)、というRPG業界でも稀有な体制で制作が続けられました。この三者協調は初めは非常に上手くいっていましたが、しかし作品世界を動かす権限を終始GDWが握っていたことが、彼らの関係を徐々に歪にしていったのです。
ファンジンでは『Jumpspace』(全6号)、『Security Leak』(全5号)、およびジオ・ジリナスによる『Traveller Times』が創刊されています。特に『Traveller Times』は、途中『Terra Traveller Times』と名を変えて1991年まで存続しました。紙としては全43号が刊行され、以後電子化がなされましたが現在では全て消失しています。
なお余談ですが、この頃ジョー・フューゲートは公式設定にある単語や文法を用いて、まるでヴァルグルのように喋ることができるようになりました。ただし喉に非常に負担がかかり、日頃の練習が欠かせないようです。
【1988年】
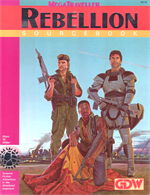 GDWから『Rebellion Sourcebook(反乱軍ソースブック)』と『Referee's Companion』が発売されました。前者は反乱の経緯や各反乱勢力の解説、後者はボックスセットに収まり切らなかった各種設定情報(エイリアン・モジュール総集編など)やルールが詳述されています。
GDWから『Rebellion Sourcebook(反乱軍ソースブック)』と『Referee's Companion』が発売されました。前者は反乱の経緯や各反乱勢力の解説、後者はボックスセットに収まり切らなかった各種設定情報(エイリアン・モジュール総集編など)やルールが詳述されています。DGPからは車両データ集『101 Vehicles』、入手困難だった「グランドツアー」第1話~第4話をまとめた単行本『The Early Adventures』、レフリー・スクリーンに加えて(ザルシャガル宙域を舞台にした唯一の)シナリオ小冊子が付属した『Referee's Gaming Kit』、宇宙船運用ルール・設定集『Starship Operator's Manual Vol.1』が発売されました。
『Challenge』誌が季刊から隔月刊に移行しました。また、第34号から誌面内の『Traveller』表記が『MegaTraveller』に切り替わり、第35号からはGDW製に限らないSF-RPG総合誌として再編されました。これはかなり異例なことではありますが、意図としては他社ゲームのファンをGDW作品に引き込むことが推察されます。自社製RPGを優先的に扱う方針に変化こそなかったものの、相対的に『メガトラベラー』の地位が低下したともいえます。
日本では『タクテクス』第58号から「グランドツアー」の翻訳連載が開始されています。年末には『トラベラー・アドベンチャー』も発売されました。
【1989年】
GDWから『COACC』が発売されました。惑星の大気圏と低軌道を守る「空軍」に焦点を当てた初の資料集で、解説と様々なデータが収録されています。
製品番号から推測すると、この『COACC』の次には『Flashback: Historical Adventuring in the Imperium's Past』というシナリオ集が計画されていました。PCは冷凍睡眠による時間旅行者となって、恒星間戦争、暗黒時代の始まり、帝国建国、内乱の始まりと終わり、超能力弾圧、ソロマニ・リム戦争といった歴史的事件に立ち会い、最終的に帝国暦1300年の未来から「過去」を俯瞰する、という構成だったようです。この企画は1992年に再浮上したようですが、結局この時も立ち消えとなりました。
DGPからは『World Builder's Handbook』が出されました。これは『トラベラー』時代の資料集『Grand Survey』『Grand Census』(1986年~1987年)を合本して調整を施したもので、半分は偵察局による惑星探査活動の解説や追加装備、残りの半分はかつての『偵察局』や『メガトラベラー』搭載の上級星系作成システムよりも詳細な、星系の文化や宗教観にまで踏み込んだ作成のできる改定ルールが収められています。
『Challenge』第39号に「Special Supplement: The Hinterworlds」が掲載されました。ヒンターワールズは中立星系や小国家群が多くを占める宙域で、〈帝国〉の反乱から離れたい人々(と新規入門者)に向けて掲載されたようです。宙域の歴史や小国家の解説、かつての『Supplement 3: The Spinward Marches』と同等の宙域内全UWPや星域情報が収められています。
そしてこの号から後、チャールズ・ギャノン(Charles E. Gannon)によるヒンターワールズ宙域を舞台にしたショートシナリオが少しの間掲載されるようになります。
Paragon Softwareが『トラベラー』初のコンピュータゲーム『MegaTraveller 1: The Zhodani Conspiracy』を開発しました(販売はMicroproseから)。『メガトラベラー』のルール自体を(簡略化しながらも)そのまま取り込んだことに称賛の声が挙がったものの、一方で戦闘システムの作りがまずく、『Computer Gaming World』誌では「歴代4位の酷いゲーム」と(1996年発売の第148号にて)評されてしまいました。
ちなみにこれは、『メガトラベラー』を冠しながらも反乱以前の時代を描いた唯一の作品です。
パソコン通信GEnieに、ジョー・フューゲートが『Atlas of the Imperium』を基にした膨大な量のUWPデータを公開しました(DGPからフロッピーディスクで販売する予定でしたが、実現しませんでした)。1994年にGEnieのFTPサーバーであるSunbaneに転載されて広まったことから今では「Sunbane」と呼ばれるこの標準世界書式(UWP)集は、欠けた部分を補う手法の違いで幾つかの派生版を産みましたが、現在にまで至る既知宇宙設定の根幹を成す最重要資料となりました。ただしデルファイ宙域のUWPに「10043」が多発したり、マッシリア宙域にTL16世界が乱立したりしたのは、当時から問題視されていました。
日本では『タクテクス』誌の「グランドツアー」連載が第6話をもって事実上打ち切られ(ただし第6話として掲載されたものは本当は第7話です)、佐脇洋平による『メガトラベラー』紹介連載に切り替えられました。また、ホビージャパン版『トラベラー』としては最後のサプリメント『トラベラー・ロボットマニュアル』が発売されています。日本でもいよいよ『メガトラベラー』時代の到来となるのですが、諸事情により発売までは随分と待たされることになります(その間は細々とTNSの翻訳記事が掲載されました)。
一方で、Diseños Orbitales社からスペイン語版『トラベラー』が発売されました(※1987年の段階でミラーが言及しているのでかなり遅れたようです)。内容は1977年版の翻訳らしいのですが、表紙も含めて再編集が行われ、チャート小冊子やスペイン語版のスピンワード・マーチ宙域図、珍しいものとしてはペーパーフィギュアが付属していました。
その後は『Suplemento 1: 1001 Personajes』『Aventura 1: Kinunir』『Libro 4: Mercenario』が発売されたものの、そこで展開は途絶えました。
【1990年】
 GDWから艦船データ集『Fighting Ships of the Shattered Imperium』、キャンペーン・シナリオ『Knightfall(ナイトフォール)』が発売されました。後者は反乱激戦区のマッシリア宙域で行方不明となった貴族の謎を追う話なのですが、日本語訳された際に随所に訳者から指摘が入るという穴だらけの展開と、まさに労多くして功少なしな締め方は、各地で数々の悲喜劇を生んだようです。実はこの作品は「太古種族の秘密」に代わる新シリーズの序章に過ぎなかったのですが、続きや結末が明らかになることは結局ありませんでした。
GDWから艦船データ集『Fighting Ships of the Shattered Imperium』、キャンペーン・シナリオ『Knightfall(ナイトフォール)』が発売されました。後者は反乱激戦区のマッシリア宙域で行方不明となった貴族の謎を追う話なのですが、日本語訳された際に随所に訳者から指摘が入るという穴だらけの展開と、まさに労多くして功少なしな締め方は、各地で数々の悲喜劇を生んだようです。実はこの作品は「太古種族の秘密」に代わる新シリーズの序章に過ぎなかったのですが、続きや結末が明らかになることは結局ありませんでした。ちなみに『Knightfall』以降のGDW製品は、全て発行部数が5000部に減らされています。『トラベラー』時代は1万部を切ることがなかったことを考えると、寂しい数字ではあります。
DGPからはまず、ヴランド宙域を舞台にしたキャンペーン・シナリオ集『The Flaming Eye』が登場しています。前述の『Knightfall』もそうですが、DGPが提唱した「ナゲット・システム」によるシナリオ進行が特徴です。
そして『メガトラベラー』版エイリアン・モジュールである「MegaTraveller Alien」シリーズの刊行が『Vilani & Vargr: The Coreward Races』から始まりました。その質は極めて高く、特にヴィラニ人に関する設定資料は現時点ではこの本だけという貴重なものです。そして翌年には第2弾の『Solomani & Aslan: The Rimward Races』も発売されています。
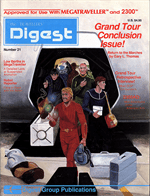 雑誌『Travellers' Digest』の方では、第21号をもって「グランドツアー」が(作品内で)12年間に及んだ長旅を終えて遂に完結し、翌年発売分からは『MegaTraveller Journal』に改題して主にデネブ領域の設定掘り下げに特化しました。
雑誌『Travellers' Digest』の方では、第21号をもって「グランドツアー」が(作品内で)12年間に及んだ長旅を終えて遂に完結し、翌年発売分からは『MegaTraveller Journal』に改題して主にデネブ領域の設定掘り下げに特化しました。(※なお日本では『タクテクス』第74号において、「グランドツアーの面々も、ダイジェスト誌11号以後は崩壊した帝国での冒険を続けています」との情報が流されましたが、最終話は帝国暦1112年なので当然崩壊はしていません。問題の第11号から対応システムが『メガトラベラー』に移行したことによる勘違いと思われます)
この年からAdjutantという(自費出版同然の)ところから『Striker』用の車両・航空機データ集が、翌年まで全10冊が刊行されました。
また、RAFM社からは28mmサイズの宇宙船メタルフィギュアの製造・販売が始まっています。最終的に30種類ほど制作されたようです。
『Challenge』第43号から編集長が交代し、長年編集長を務めたローレン・ワイズマンは副編集長に退きました。
また、『Far & Away』誌が創刊されています。キース兄弟が記事や表紙に参加し、雑誌広告も打つなど華々しくデビューしましたが、発行はわずか第2号で潰えたようです。ファンジン『Coreward』も創刊されました(これも全2号でしたが)。
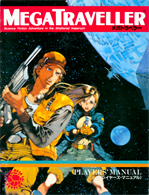


年末、日本語版『メガトラベラー スターターセット』がホビージャパンから発売され、それを受けて『RPGマガジン』第9号にて特集記事が組まれました。(日本語版全てで)翻訳は佐脇洋平が、表紙絵は漫画家・山田章博が手掛けています。しかし原文由来の多くの誤植に加えて日本語版固有の誤植も抱えてしまい、その訂正は有志がパソコン通信上で行った上で、1993年発売『RPGマガジン』第39号~第41号掲載の「メガトラベラー正誤表」まで待つことになります(そしてその後、正誤表を小冊子として添付した単品売り版が販売されました)。
また、富士見書房から小説『トラベラー(1) 戦乱のアウトリーチ宙域』が発売されましたが、これは前述の「Not in Our Stars」を佐脇洋平が和訳したものです。翌年には『逃亡の惑星(Become the Hunted)』も刊行されましたが、展開はそこで途絶えました。
(※解説文を寄せた安田均が「(著者は)いまは“メガトラベラー”小説に取り組んでいる」と記しているのは、「別の出版社(※New Infinities Productionsのこと)」から出された「同じシリーズ」の数を「二冊」としていることから、1988年に既に発売されている『Tales of Concordat, Book 3: Revolt and Rebirth』を指してしまっていると思われます)
余談ですが、Steve Jackson Gamesのスティーブ・ジャクソンは自社紙『Roleplayer』第19号において、1981年発売の第2版が絶版になって以降幻となっていた『Triplanetary』の復活を宣言します。「オリジンズ'89」の会場でマーク・ミラーと交渉して後に権利を得たこと、1991年に発売の見込みであること、単なる復刻ではなく自社のGURPS Spaceとの連携も企図した改定がなされることが明かされました。
……が、後に追信として、当時のSJGはかの「合衆国シークレットサービス強制捜査事件」の渦中にあったこと、また試作はなされたものの社外での試遊は行われなかったことが記され、結局『Triplanetary』が復活することはありませんでした。
【1991年】
この年はGDWにとって、様々な意味で転機となる年となりました。まず8月発売予定で制作が進んでいたシナリオ集『Rebels’ Tales』が4月に中止され、製品番号に2つ目の欠番が生じました。これは元々「Rebellion Sourcebook 2」として企画され、帝国暦1125年までの反乱の推移とその時代のショートシナリオ数本を収める予定でした。しかしマーク・ミラーは、そもそもこの本の必要性には懐疑的だったと伝えられています。
そしてそのマーク・ミラーが、この年GDWを退社しています。彼は当時副業で保険代理店を営んでおり、そちらに専念してGDWから給与を受け取ることをやめたのです。依然としてミラーはGDWの大株主であったので会社に対する影響力は保持していたものの、彼の退社に前後して『メガトラベラー』に、そして目をかけていたDGPに重大な影響がありました。
実のところ、GDWは売上不振から1990年の段階で事業閉鎖を考えていました。ウォーゲームは全盛期の2割に落ち込み、『Twilight: 2000』はまだまだ現役なものの、不振だった『2300AD』や『Space: 1889』は前年で新製品の投入をやめてしまいました。
SF-RPG界隈も大きく変わっていました。特に1988年発売の『Cyberpunk』(R. Talsorian Games)が火付け役となった「サイバーパンク」の隆盛はスペースオペラを過去のものとし、一方でそのスペースオペラもWest End Gamesの『Star Wars』(1987年)に大きく侵食されていました。
しかし、1990年8月に起きたイラクによるクウェート侵攻がGDWの転機となります。1991年1月初頭にフランク・チャドウィックが書き下ろした『The Desert Shield Fact Book』が、同月17日のアメリカ軍による「砂漠の嵐作戦」開始によって大ベストセラーとなったのです。ニューヨーク・タイムズ紙による売上ランキング1位を獲得し、ある意味GDW最大のヒット作と言えるかもしれません。この本で得た多額の資金で息を吹き返したGDWは、社員や設備を増強して反転攻勢を狙います。
 ミラーに代わって『メガトラベラー』の担当となった新規雇用者デイビッド・ニールセン(David Nilsen)が9月末に初出社した際に見たものは、数枚の「崩壊した帝国」図を含むイラストと、表紙原稿のコピー、そして倉庫にあった5000部分の完成した表紙カバーでした。そして彼に与えられた仕事は、来る出版のために原稿を編集することでした。
ミラーに代わって『メガトラベラー』の担当となった新規雇用者デイビッド・ニールセン(David Nilsen)が9月末に初出社した際に見たものは、数枚の「崩壊した帝国」図を含むイラストと、表紙原稿のコピー、そして倉庫にあった5000部分の完成した表紙カバーでした。そして彼に与えられた仕事は、来る出版のために原稿を編集することでした。実はGDWはミラーの退社前にチャールズ・ギャノンを中心にして、従来と異なりDGP関係者を一切使わずに(※一部のHIWG会員は関わっています)この『Hard Times(ハードタイムズ)』を、そしてそれに続く2作品を書き上げさせていたのです。
ミラーやDGPはそれぞれ、(少なくともミラーは1988年の段階で)帝国暦1125年時点での反乱終結の構想を持っていました。ミラーは、ストレフォンとマーガレットの滅亡、ソロマニ占領地の中で孤立したヴェガ自治区と〈帝国〉中央を繋ぐ1本の「スター・レーン」というアイデアを持ち、一方DGPは、ダイベイの陥落、デュリナー=マーガレット同盟とソロマニ連合との停戦合意、アンタレスの超新星爆発による滅亡、といういずれも「小国分裂による現状維持」を思い描いていました。
しかしギャノンがミラーに提示したものはそれらよりも遥かに過酷で現実的な、〈帝国〉が軍事的ではなく経済的に自壊するというものでした。ミラーはそれを認めて自身の「1125年停戦」構想を取り消し、『Rebels’ Tales』の発売中止に至ったと思われます。
「マークはどんな構想に対しても寛大で、私の創造性を抑え込んだりもみ消したりするような職権は決して用いなかった」
(チャールズ・ギャノン)
この『Hard Times』によって、設定は反乱の最中の帝国暦1122年から一気に1128年に進み、もはや反乱勢力の誰も〈帝国〉の再興は望めない、荒廃した「苦難の時代」が描かれました。国家に代わって個人(つまりプレイヤーが)が英雄となりやすくなることを企図した激変でしたが、これによりDGPは深刻な打撃を受けます。これまでのミラーを間に入れたGDWとの協調体制を反故にされただけでなく、発売を準備していた資料集・シナリオが路線変更によって出版する機会を逸してしまったのです。
1990年の段階で、DGPは以下の作品の出版計画を持っていました。
『Campaign Sourcebook 1: The Black Duke』:
1989年末発売予定。イレリシュ宙域を舞台にした『トラベラー・アドベンチャー』型の商人キャンペーン・シナリオで、前述のデュリナー=マーガレット同盟締結の話にも触れられるはずでした。1990年に入って『Rebels’ Tales』との入れ替えでキャンセルされたようです(※この時に同時に、『Knightfall』や『Solomani & Aslan』とも絡めたDGP側の反乱終結構想も立ち消えとなったと思われます)。
『Manhunt』:
キャンペーンシナリオ「Onnesium Quest」三部作の第1部で、Gen Con '90(1990年8月)で発売予定でした。銀河で最も希少な物質「オンネシウム118」が多く眠るとされる伝説の小惑星帯ははたしてどこに? そして、鉱脈を見つけたと言い残した宇宙鉱夫はどこに消えたのか? 第2部『Antares Down』も1990年秋発売予定だったようです。
『Robots & Cyborgs』:
1990年夏発売予定。ロボット作成ルールの改定と人体の機械化ルールの追加、『101ロボット』相当のロボット型録を収録する予定でした。ロボット作成ルールに関しては2011年に草稿が発掘され、有志によって『MegaTraveller Robots: Shudusham Concords Revisted』として編纂されました。
『Grand Explorations』:
1990年夏発売予定。深宇宙探査や植民地化の解説、未知世界用に調整された星系作成システム、探査シナリオに向いたフラニ宙域の設定と新知的種族、4つの探検シナリオが収録される予定でした。
『Starship Operator's Manual Vol.2』:
1990年秋~冬発売予定。ジャンプドライブや宇宙船整備についての解説、宇宙船の入手について、宇宙船の駆動方式について、100トン偵察艦の派生型等々が盛り込まれる予定でした。
他にも「Alien」シリーズの第3~5巻である『Zhodani & Droyne: The Psionic Races』『K'kree & Hiver: The Exotic Races』『Humans & Nonhumans: The Minor Races』、反乱の主役たちのインタビュー記事を中心に構成した総集編『The Best of the Travellers' Digest』が1991年以降の発売予定で計画が組まれていましたが、これら全てが「時期外れ」となってしまいました。これら未発売作品の原稿料などによって、DGPの財務は大きく苦しめられました。結果的にDGPから出たサプリメント本はこの年発売の『Solomani & Aslan』が最後となり、その後は『MegaTraveller Journal』の発行に専念しつつ、裏でとある企画を動かしていました……。
この年、SeekerがSeeker Gaming Systemsに社名変更しています。SGSは1985年の創業以来『Research Facility』『Empress Marava』『Gazelle Class Close Escort』といった、『メガトラベラー』(や『2300AD』)向けに様々な建物や艦船のデッキプラン(兼ミニチュアゲーム用ゲームボード)を提供してきました。また、表紙にウィリアム・キースを起用するなどキース兄弟とも近く、彼らが版権を持つ「スコティアン・ハントレス号」シリーズなどの復刻も手掛けています。
しかし翌1992年に活動を停止してしまいました。
『メガトラベラー』の広報紙『Imperial Lines』がGDWから発刊されました(実質HIWG制作ですが)。8頁の中に設定や追加装備、ショートシナリオが収録されています。また、スピンワード・マーチ宙域に隣接する「フォーイーヴン宙域」の設定作りを個々のレフリーやプレイヤーに正式に委ねた、後の「Free Sector宣言」に繋がる重要資料も掲載されています。
なお、第2号も年内に公開されたものの、1992年6月発行予定だった第3号は延期され、第3/4号合併号として仕切り直して同年11月発行に向けて制作が続けられましたが、結局幻となりました(第5号の計画もあったようです)。
 日本では9月に『反乱軍ソースブック』が発売されています。また、『RPGマガジン』ではキャンペーン・シナリオ「ガシェメグの嵐」が連載されました(全9話)。シナリオの舞台となる「ガシェメグ宙域」はマーク・ミラーの許可を得て日本独自設定での展開がなされ、簡素ながら一部の星域図・UWPの公開もされています。
日本では9月に『反乱軍ソースブック』が発売されています。また、『RPGマガジン』ではキャンペーン・シナリオ「ガシェメグの嵐」が連載されました(全9話)。シナリオの舞台となる「ガシェメグ宙域」はマーク・ミラーの許可を得て日本独自設定での展開がなされ、簡素ながら一部の星域図・UWPの公開もされています。(※ちなみにこの「ガシェメグの嵐」では“「本物の」ストレフォンはクローン”説が採用されていますが、一方HIWGではエド・エドワーズが“「本物の」ストレフォンはクローンだが、暗殺されたストレフォンも実はクローン(オリジナルは10年前に死亡)で、ルカンに捕殺されなかったクローンがあと1人行方不明となっている(しかも超能力者)”という設定を起こしています。そしてGDWは……)
ドイツ語版『トラベラー』最後の作品『Splitter des Imperiums』が発売されました。これは『トラベラー』と『メガトラベラー』の橋渡しをする独自編集本で(といってもJTAS誌の翻訳記事も多いですが)、ルールの変更点の解説、デッキプラン、異星生物などが収録されています。
ドイツでは(と言うより日本以外では)『メガトラベラー』は翻訳されなかったため、ドイツでの『トラベラー』の展開はこれで一旦途絶えることになります。
マーク・ミラーによると、1991年末以降の発売予定で『トラベラー』初の公式小説が企画されていたようです。ヒューゴー賞受賞の大物編集者が携わり、大手出版社から様々なテーマ(太古種族、第五次辺境戦争、反乱等々)の小説が出るようでしたが、結局何一つ発売はされませんでした。
コンピュータゲーム第2弾である『MegaTraveller 2: Quest for the Ancients』が発売されました。前作の反省を活かしてシステムを刷新し、またマーク・ミラーが直接製作に関与しています(前作では資料提供のみ)。今回は上々の評価を得られ、直接の続編である『MegaTraveller 3: The Unknown Worlds』の制作も予告されましたが、1992年に製作元のParagonがMicroproseに買収されたのが響いてか、結局発売されることはありませんでした。
【1992年】
「我が社の製品名がこれから起こることを不気味に暗示していた。『苦難の時代(Hard Times)』『荒れ狂う波(Troubled Waters)』『危険な旅路(Dangerous Journeys)』『異議あり(Challenge)』と……」
(デイビッド・ニールセン)
『ハードタイムズ』時代としては初の(そしてGDWとしても初の二つ折り判の)シナリオ集『Assignment: Vigilante』が発売されます。荒廃したディアスポラ宙域を征く星間傭兵ヴィジランテの活躍を描いたこの作品ですが、著者のはずであるチャールズ・ギャノンは「自分の原稿の大部分が削除され、『劇的に』書き直された」と後に語っています。同じく発売された宙域設定集『Astrogator's Guide to the Diaspora Sector』についても「希望の兆しを示すはずだった」と振り返っています。
というのも、ギャノンはまず『ハードタイムズ』で反乱を事実上終結させ、その後の200年に及ぶ復興期を新作「Surveyor」で描く構想を持っていました(『ハードタイムズ』本文中にもその伏線が伺えます)。また、フランク・チャドウィックが1990年頃から開発を進めていたものの発売中止となったミニチュアゲーム「Star Viking」は、その中間の帝国暦1130年頃に位置付けられることになっていたようです。これにはGrenadier社との提携も見据えていた上に、ギャノンによる小説執筆の契約もされていました。
ギャノンの構想では、サーベイヤー(探査者)たちが傭兵スター・ヴァイキングと共に、かつての『リヴァイアサン』のように未知と化したも同然の危険な宇宙の荒野に飛び込み、海賊らと戦って人々を助け、やがて復興と成長を遂げた彼らの前に機械の体で永遠の命を得たルカン率いる「暗黒帝国」が立ち塞がり、イリジウム玉座の奪還を目指す戦いが始まる……というものだったようです。
「イリジウム玉座への帰還は新たな帝国を象徴していただろうし、“短い夜”の終わりを明示したことだろう。もっとも、それが良い企画だったかどうかは全く別の問題だが……」
(チャールズ・ギャノン)
しかし、ギャノンのGDWでの仕事はミラーの退社とともに終了しています。なぜなら1991年から開発が始まったとされる新作“Traveller: Take 3”は、彼が全く想定していなかった「新時代」を舞台としていたからです。
「事実、JTASやChallenge誌の一番人気はトラベラー・ニュースサービスだった。彼ら(GDW)のファンは彼らが築いた宇宙を熱愛していたのに、その歴史を根本的に終わらせて別のものとして再開させるのは、それに至った議論は理解するにしても決して理解できない商売上の決定だったと思う」
(チャールズ・ギャノン)
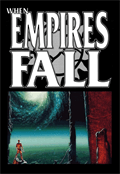 9月発売の『Challenge』第64号に、突如として「When Empires Fall」という8頁の記事が掲載されます。その内容は、何かを示唆した詩、「帝国暦1130年、〈帝国〉は滅んだ。」という衝撃の一文から始まる文章、そして人工知能や宇宙船の自動応答装置(transponder)に関する設定が記され、最後に『Twilight: 2000』第2版由来のゲームシステムを搭載した『Traveller: The New Era』が1993年2月に発売される(※実際は6月までずれ込みました)という予告が載りました。
9月発売の『Challenge』第64号に、突如として「When Empires Fall」という8頁の記事が掲載されます。その内容は、何かを示唆した詩、「帝国暦1130年、〈帝国〉は滅んだ。」という衝撃の一文から始まる文章、そして人工知能や宇宙船の自動応答装置(transponder)に関する設定が記され、最後に『Twilight: 2000』第2版由来のゲームシステムを搭載した『Traveller: The New Era』が1993年2月に発売される(※実際は6月までずれ込みました)という予告が載りました。こうして反乱は、そして『メガトラベラー』は事実上の終焉を迎えたのです。この路線変更がミラーの退社後に行われたのは間違いありません。これがミラー主導なのかGDW主導なのかははっきりしていませんが、ギャノンの証言の中でミラーが以前から“Traveller 3rd Edition”を準備していたくだりがあるので、ミラー退社後にGDW側で“3rd Edition”が“Take 3”に差し替えられた可能性は高そうです。また、HIWG会員は1991年末の段階で路線変更のことを知らされています。
「ノリスに伝えてくれ。すまなかった、と――」
(皇帝ストレフォンの遺言)
GDWが制作した最後の『メガトラベラー』作品である『Arrival Vengeance: The Final Odyssey』は、ノリス大公の特命を受けて3年間に及ぶ航海に旅立ったライトニング級巡洋艦アライバル・ヴェンジェンスの軌跡を体験するシナリオ(の概要)集です。かつての「グランドツアー」とは奇しくも逆回りに、ある「重要人物」と共にデネブ領域を出てアスラン領を経由し、ワリニア公クレイグやデルファイ公マーガレットといった反乱の当事者と会見し、荒廃した帝国中央を突っ切り、最後は「本物の」ストレフォンに「託されて」大裂溝を踏破してデネブに帰還する……という、来るべき「新時代」に向けての地ならしと伏線張りの要素が強く感じられます。また、長らく秘密にされてきた「本物の」ストレフォンの正体が明かされるという意味でも重要な資料です(とはいえ、今さら明かされてもどうにもなりませんが……)。

 日本では『ナイトフォール』が発売され、『RPGマガジン』にてリプレイ『サイオニック・バスターズ!』が連載開始されました(全6回)。反乱とは距離を置き、超能力者PCたちが同じく超能力を駆使する宗教団体への潜入任務を行うという派手さを求めた、ある意味「邪道」(本文より)な話でした。
日本では『ナイトフォール』が発売され、『RPGマガジン』にてリプレイ『サイオニック・バスターズ!』が連載開始されました(全6回)。反乱とは距離を置き、超能力者PCたちが同じく超能力を駆使する宗教団体への潜入任務を行うという派手さを求めた、ある意味「邪道」(本文より)な話でした。そして、このリプレイ連載終了と共に『RPGマガジン』での記事掲載は散発的となり、翌年発売の第44号の記事と『ハードタイムズ』の発売をもって日本における『メガトラベラー』は終了します。構想では日本独自のレフリー・スクリーン、「ガシェメグの嵐」の単行本化、『Referee's Companion』や『The Flaming Eye』の翻訳が挙げられていましたが、全て幻となりました。
【1993年】
Sword of the Knight Publicationsから『Traveller Chronicle』誌が創刊されました(刊行数は年2~4)。掲載された重要資料としては、かつてFASAが展開していたファー・フロンティア宙域の設定紹介や、チャールズ・ギャノン自らが執筆した「Astrogator's Update to Diaspora Sector」、リーヴァーズ・ディープ宙域の幻の設定集「A Pilot's Guide to the Caledon Subsector」が挙げられます。
米国のヘビーメタルバンド「The Lord Weird Slough Feg(現Slough Feg)」は、文字通り『トラベラー』を主題としたアルバム『Traveller』をリリースしました。「The Spinward Marches」「High Passage/Low Passage」「Vargr Moon」といった曲が12曲収められています。各地の批評を見る限りでは、音楽ファンから非常に好評をもって受け入れられたようです。
 前号から1年振りに発行された『MegaTraveller Journal』第4号には、ウィリアム・キース書き下ろしの大規模キャンペーン・シナリオ「Lords of Thunder」が丸々収録されました。これは元々SGSから発売する予定だったものを買い入れた、という経緯があります。旅の舞台はゲイトウェイ宙域に(Judges Guildのものに上書きして)設定され、これまで距離的事情から絡みの少なかった知的種族ククリーが大きく関わってきます。
前号から1年振りに発行された『MegaTraveller Journal』第4号には、ウィリアム・キース書き下ろしの大規模キャンペーン・シナリオ「Lords of Thunder」が丸々収録されました。これは元々SGSから発売する予定だったものを買い入れた、という経緯があります。旅の舞台はゲイトウェイ宙域に(Judges Guildのものに上書きして)設定され、これまで距離的事情から絡みの少なかった知的種族ククリーが大きく関わってきます。ちなみにこの「Lords of Thunder」が、長らく『トラベラー』を支え続けたウィリアム・キースにとって最後の作品となりました。その後、ウィリアムは以前から平行して手掛けていた小説業に専念して数々の作品を残します。
「『Traveller: The New Era』の登場で、我々は『トラベラー』のサポートをやめることにしました。これには多くの理由がありますが、最も重要なのはゲームの針路を自分たちで決めたいという望みです」
(ジョー・フューゲート)
そしてこの第4号は、DGP最後の出版物でもありました。いえ、彼らはこれを最後にする気はなかったのです。彼らは『A.I.』という超未来(もしくは超過去)の「サイエンス・ファンタジーRPG」を計画し、着々と準備を進めていました。当初予定では1991年10月の発売で、それから遅れに遅れてはいたものの雑誌やイベント会場で広報活動を念入りに行い、華々しく発売させるはずでした。DGPの悲劇は、優れたゲームシステムや設定をいくら作り出しても、ゲームの「針路」自体を自分たちで決められずに翻弄されたことにありました。自社作品の『A.I.』なら、それができるはずだったのです。
しかし、信じがたいことに『A.I.』の原稿を収めたハードディスクが破損する事故により、出版は頓挫してしまいます。この話が本当かどうかはさて置いても、『A.I.』を出せずに借入れ金を返済する見込みがなくなったDGPは、いくつかの原稿料遅配トラブルを抱えつつ、ジョー・フューゲート1人だけの債権整理企業として消えていきました……。
……が、まだDGPをめぐる物語は終わりません。1994年にフューゲートのもとをロジャー・サンガー(Roger Sanger)なる者(※といってもHIWG会員だと思われます)が訪れ、DGPの資産(版権や商標を含む)の買収を持ち掛けます。9ヵ月間に及ぶ交渉の末、数千ドルでDGPはサンガーの物となりました。その後のフューゲートはゲーム業界から身を引き、趣味だった鉄道模型の世界で活躍しています。
そして1996年、サンガーとDGPが歴史の表舞台にもう一度だけ現れるのですが……その前に「新時代」について語らねばなりません。「新時代」がもたらしたものは、反乱以上の混乱と凋落だったのです。
「もうよせ、報道を止めても無駄だ。全てが終わったんだ」
(帝国暦1130年243日付TNS記事より)
(「トラベラー40年史(3) 新時代、そして暗黒時代へ…」に続く)
(文中敬称略)